首都高速 → 東北道 宇都宮IC → 日光宇都宮道路 今市IC → 国道121号 →
日塩もみじライン → 国道400号 → 県道17号 → ボルケーノハイウェイ →
茶臼岳(散策) → 県道17号 → 東北道 那須IC → 首都高速
という往復およそ400km弱である。
日曜日だったが、前日がとてもきれいな秋晴れの一日だったので、渋滞するのが恐ろしくて7時過ぎに東京を出た。大して混んではいなかったのだが、濃い霧が東北道を覆っているところがあったので、ペースはなかなか上がらなかった。少しイライラするが、「今日はゆっくり紅葉鑑賞」と自らに言い聞かせながら、追越車線を走り続ける車の後ろで我慢をする。
 鹿沼IC近辺で、私の愛車がついに27000km走行と相成り、記念に写真を撮った。96年式なので今年で9年目、そろそろ年季が入ってきている。しかし8歳のおじいちゃんの割には機関系は絶好調で、オイルの焼ける匂いをさせながら地面と空気の隙間を切り裂くように走る。アイドリングもぶれないし、寒くなってきたので出力も夏に比べて力強くなった気がする。
鹿沼IC近辺で、私の愛車がついに27000km走行と相成り、記念に写真を撮った。96年式なので今年で9年目、そろそろ年季が入ってきている。しかし8歳のおじいちゃんの割には機関系は絶好調で、オイルの焼ける匂いをさせながら地面と空気の隙間を切り裂くように走る。アイドリングもぶれないし、寒くなってきたので出力も夏に比べて力強くなった気がする。東北道で霧が晴れると、ペースも上がってきた。宇都宮ICから日光宇都宮道路に入ると、随分と木が色づいている。出かける前に調べたら、もう見頃は過ぎたところも多かったとのことだったので、自分のエクスペクテーションを下げていたのだが、出遅れながらも何とか間に合ったのでほっとする。
一人で出かけたために中々写真が上手く撮れない。撮った写真よりは実物のほうがきれいだったので念のため。今市ICから国道121号線に入るまでは余り楽しくない道だったが、日塩もみじラインに入ると状況は一変。今日は紅葉を見に来たので飛ばさないと何度も言い聞かせながら、お年寄りの5人乗車のお尻を眺めながら走った。紅葉を見に来たわけで、もみじマークの車を鑑賞しにきたわけではないのだが。
日塩もみじラインは、結構いい。中低速コーナーが連続するスリリングな道である。ゆっくり走っていたのでどれぐらい長いかわからなかったが、調べてみると全長およそ28km。これは道が空いていればかなり力がこもるドライブになるだろう。途中では高低差のある連続ヘアピンカーブがあったりするのでなかなか面白い。HPの趣旨からするともみじラインがどのような道だったかについて詳しく書くべきなのかもしれないが、上述したとおり中々気持ちよく走ることが出来ないのでご容赦願いたい。
南斜面はまだ暖かいので綺麗に紅葉していたが、山の北側は随分と落葉していて、白樺の木の白さが目立った。色づいた葉を見るのも楽しいが、白樺の木の枝の先がまるで絵筆のように柔らかく見え、それはそれで美しかった。やはり交通量が多く、ペースが上がらないが、景色のおかげでまったくイライラしない。家を早く出たので、光線の具合か赤や黄色の葉がとても美しく見える。やはり早起きは三文の得である。


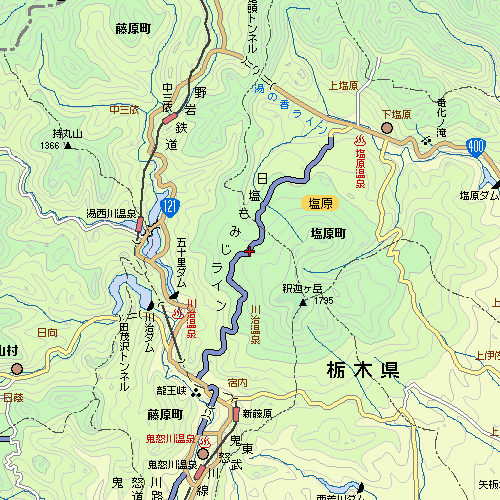

うっとりしながら運転していると、あっという間に那須まで抜けてしまった。那須の道を走っていると、自分が高原の中を走っていることを強く意識してしまう。まっすぐな道、その横に広がる牧場、草を食むホルスタイン、窓を開けていると香る田舎の香水。
いつもドライブに出かけると、どこで食事をするのかがわたしにとって極めて大事なことなのだが、今回のランチは那須の黒毛和牛が食べたいと思ったのでかなり悩ましかった。いろいろ調べてみて、「桜」というステーキの店と、モンテオブールというシチューが旨い店のどちらかがよさそうだということが分かり、結局家庭的な感じのするモンテオブールに行くことにした。那須街道の渋滞がひどく、あと数kmの所まで辿り着いてから30分ぐらいかかった。行楽地で一人で食事すると、特に混雑しているときは店に悪いなあ、と思うのだが、幸いまだ12時過ぎで、店は予想したほど人がいなかった。


モンテオブールは一軒家のレストランで、恐らく8組も入れば一杯になってしまうぐらいのこじんまりとした店。 既に11月初旬だというのに、まるで初秋の陽射しで、運転していると汗ばんでくるぐらいの陽気。折角なので、テラスの席で食事をさせてもらうことにする。上の写真で奥に見えるのが那須街道。因みにこのレストランの真横にはゴルフ練習場とショートコースがあって、テラス席からは打音が聞こえる。こちらでは和牛のシチューがお勧めだということで、4000円弱のシチューのコースを食べた。時間をかけて手作りしていることがよくわかるシチューだった。甘すぎるデミグラスソースは苦手にしているのだが、こちらのソースは玉葱の自然にやわらかい甘さで、とてもおいしくいただいた。ワインが飲めればもっとよかったのだが、それは当然叶わない。
のんびりしていると寝てしまいそうなぐらい気持ちのいい陽射しの下で食事をしていたので、那須街道の渋滞に身を委ねる元気がなかなか出てこない。こたつでうたた寝している時に早く起きろ、と言われた時のような感じ。体中のやる気を振り絞り、食事のお礼を言って、まるで真夏の炎天下に放置した後のような熱を帯びた車に乗り込んだ。
次の目的地、というかこのドライブで一番楽しみにしていた場所は、「鹿の湯」という立ち寄り湯だ。先日福島に行って硫黄泉の良さに打ちのめされて以来、立ち寄り温泉みしゅらんを見ては五つ星にレーティングされている温泉をチェックしている。鹿の湯は、PH2.8程度と極めて酸性度が強い。
カーナビには鹿の湯の登録がなかったので、少し探すのに手間取ってしまったが、それは那須湯元の名勝である殺生石の道を挟んで反対側にあった。川のほとりにあるのだが、川底からして既に硫黄で真っ白である。期待が高まった。
 川の左にあるのが受付と休憩所のある建物で、300円を払って川の上の黒光りのする木の廊下を歩いて温泉に行く。暖簾をくぐるとすぐに脱衣所があり、脱衣所と温泉との境には戸がなく、不思議な感じ。ここでは入浴に作法がある。まず、掛け湯をするのだが、掛け湯専用の湯舟があり、そこの縁に膝をかけて正座して、後頭部に大人は200回、子供は100回柄杓ないしは盥でお湯をかけるのだ。最初は、掛け湯用の湯船に自分が掛けた湯が入らないように掛け湯をしていたのだが、隣のおじさんに注意された。最初はそのおじさんが何を言っているのか全く判らなかった。というのも、元関西人の私には生粋の栃木弁は難しすぎた。何度か聞きなおした挙句、どうやらそのおじさんが言おうとしているのは、「掛け湯が湯船に戻るようにもっと頭を湯船の上に出せ」ということが判った。一度体にかかった湯が湯船に入るというのはよくないことだ、と思って一生懸命掛け湯をしていたのだが、どうやらそうではないらしい。確かに、みんなが200回も掛け湯をするのなら、すぐにお湯がなくなってしまうだろう。この不思議な掛け湯の習慣には、頭に湯を掛けることで温泉成分の含まれた蒸気を吸入することと、強い温泉成分に体を慣らす意味があるらしい。
川の左にあるのが受付と休憩所のある建物で、300円を払って川の上の黒光りのする木の廊下を歩いて温泉に行く。暖簾をくぐるとすぐに脱衣所があり、脱衣所と温泉との境には戸がなく、不思議な感じ。ここでは入浴に作法がある。まず、掛け湯をするのだが、掛け湯専用の湯舟があり、そこの縁に膝をかけて正座して、後頭部に大人は200回、子供は100回柄杓ないしは盥でお湯をかけるのだ。最初は、掛け湯用の湯船に自分が掛けた湯が入らないように掛け湯をしていたのだが、隣のおじさんに注意された。最初はそのおじさんが何を言っているのか全く判らなかった。というのも、元関西人の私には生粋の栃木弁は難しすぎた。何度か聞きなおした挙句、どうやらそのおじさんが言おうとしているのは、「掛け湯が湯船に戻るようにもっと頭を湯船の上に出せ」ということが判った。一度体にかかった湯が湯船に入るというのはよくないことだ、と思って一生懸命掛け湯をしていたのだが、どうやらそうではないらしい。確かに、みんなが200回も掛け湯をするのなら、すぐにお湯がなくなってしまうだろう。この不思議な掛け湯の習慣には、頭に湯を掛けることで温泉成分の含まれた蒸気を吸入することと、強い温泉成分に体を慣らす意味があるらしい。ようやく掛け湯が済み、温泉に浸かれる、と思ったのだが、6つある湯船のどれに入るか悩ましかった。湯船は小さく、どうやら足を抱えて4人ぎりぎりで入るのが流儀らしいということが判った。なぜ6つあるかというと、温度がそれぞれ41度、42度、43度、44度、46度、48度と分かれているのだ。奥に行けば行くほど温度が高くなっている。さらに地元の人の割合も奥に行けば行くほど高く、私のような観光客はみんななんとなく地元の人に遠慮している。因みに源泉の温度は80度弱。最初は42度の湯船からトライした。PHは強いがやわらかい、とても気持ちのいいお湯で、最初は半身浴からという案内を無視して首まで浸かって極楽気分を味わった。
鹿の湯には洗い場がなく、したがって石鹸、シャンプーは使用禁止である。床は板張りになっていて、火照った体を冷やす人たちがぺたんとお尻から座り込んでいる。私も42度のお湯にしばらく浸かり、板張りの床に腰を下ろして体を冷まし、43度、44度のお湯にチャレンジした。このくらいの温度であれば楽勝である。46度、48度の湯は一番奥まったところにあって、地元の人たちが歓談しているのでなかなか入りにくい。あまり長く入るとお湯が強いので却って体に毒であるらしく、地元の人たちはわざわざ3分の砂時計を持ってきて、熱い湯に時間を計って入っていた。また地元の人はペットボトルに氷水を入れて持ってきていた。さすがにどんなに慣れているとはいえ48度のお湯には地元の人でもそうそう浸かっていられないらしい。
少し空いたタイミングを見計らって、遠慮しながら46度のお湯に浸かってみた。確かに熱いが、耐えられないほどではない。「なーんだ大した事ないじゃん」と思って入っていたら、電子温度計を持ったおじさんがやってきた。一緒に入っている人が「何度?」と聞くと「45度ぴったり」との答え。じゃあ、といって雨どいのようなもので源泉が引かれているところから私の入っている湯船にお湯を入れてくれた。一気にお湯の白濁度が上がり、湯の花の結晶が湯の表面に現れ、そして、当たり前だがどんどんお湯が熱くなっていった。なんというのだろう、熱い、というかぴりぴりするというか不思議な感じである。そしておじさんは湯温がきっちり46度になるまで源泉を注いでくれた。
隣に入っているおじさんに「熱いですねえ」と話しかけると「まだまだ」との答え。何で男はサウナでも温泉でも、後から来た人よりも先に出るのはかっこ悪いことだと思って痩せ我慢してしまうのだろう。私もかなり痩せ我慢を続けていたのだが、あまり長く入っていると逆に体に悪いから、と自分に言い訳して湯から出ることにした。本当に硫黄が強い湯だったので、二日経っても体から匂いが取れなかった。
温泉を満喫して、すぐ近くの殺生石と教傳地蔵を見て、温泉神社に参詣した。江戸時代に松尾芭蕉が鹿の湯、殺生石の近くを訪れたときに「蜂や蝶の屍骸が地面が見えないぐらい積み重なっている」と評したぐらい、昔は温泉ガスがきつく、人が亡くなることもままあったらしい。そのため、昔の人は自然の力を心から畏れて、供養を行っていたそうだ。


本来であれば茶臼岳の頂上にロープウェイで上り、2時間ほどのハイキングを楽しむ予定だったのだが、ボルケーノハイウェイでロープウェイの駐車場待ちの車が列を成しており、我慢できずに帰ることにした。
2時半過ぎに帰路につき、那須街道を戻ってみると、反対車線は引き続き大渋滞。モンテオブールの店先には順番待ちのお客さんが溢れていた。那須は国定公園に指定されているので、屋外広告物に規制があるため、セブンイレブンの看板の普通なら赤い部分が茶色だったのがおかしかった。
来年はちゃんと10月後半に山登りを兼ねて、日塩もみじラインを走ろうと思う。鹿の湯も48度にチャレンジしないと。やることが多すぎて忙しすぎるのだが。