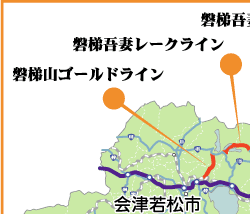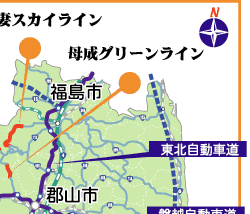紺ガエル日記 2004年9月5日 裏磐梯グランドツーリング
走行距離 26,150km
ENGINE9月号グランド・ツーリング特集で、「ALFA GTで行く会津磐梯山への旅」という記事があった。かつてZ3時代に裏磐梯を走ったことを思い出し、また、記事扉写真の東鉢山七曲りの写真が素晴らしかったため、どうしても再訪したくなり、週末一人だったことをいいことに会社の後輩を無理やり巻き添えにして一路福島に向かうことにした。
当初予定ルートは以下の通り。
一日目: 首都高から東北自動車道で福島西IC(255km、高速料金6500円)、その後磐梯吾妻スカイラインを経由しホテルプルミエール箕輪泊
二日目: 磐梯吾妻レークライン、桧原湖経由で西吾妻スカイバレーを登り、折り返して 磐梯山ゴールドライン経由で磐梯河東ICから帰京(260km、6600円)
(ちなみに以下の地図は福島県道路公社のHPからの借り物です)
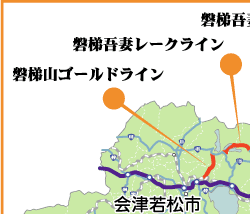
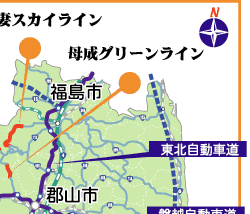


ギターのレッスンがあるため、初日の出発は1時過ぎとなった。あいにく予報は曇りのち雨。後輩をピックアップし、目黒のラーメン次郎で腹ごしらえをすると時計は2時を回ってしまい、男二人ニンニク臭くなりながら慌てて福島を目指すことにした。
かつてZ3で五色沼を訪れた時には、「踏んでも踏んでも着かない」と思われた裏磐梯だった。その記憶があるので東北道のオービスの位置を完全に確認し、助手席の後輩に1km前からコールするよう厳命して右足に力をこめて福島を目指した。ちなみに目的地までのオービスは4箇所。しかし途中から大雨。宇都宮ICを越えたらバケツをひっくり返すような雨に襲われた。交通情報を聞くと何と大雨洪水警報が出ているとのこと。出来れば日没までに磐梯吾妻スカイラインを走りたかったのだが、現実には難しいと判った。
オービス以外にも覆面PCにも気をつけながら走った。「R33のスカイラインには気をつけないと」と話すと、R32のスカイラインのGTEマニュアルという今ではかなり奇特な車を運転している後輩は興味深々で、彼が走行車線を流しているR33を発見したために減速したら、ただの一般市民だった。ある意味がっかり(?)したが気を取り直して走っていると、その直後にR33の覆面に捕まっている車を発見。後輩は大喜びだった。何故喜ぶかは不明。
福島西ICに着いた頃には雨が降っていたこともあり既に薄暗くなってきてしまっていた。そこから20分ほど山道を走る。中低速コーナーが連続する結構面白い道が続くのだが、霧がかかってきてしまったため余りペースが上がらない。山を登っていくうちにどんどん乳白色の塊を切り裂きながら走っているような気がしてきた。途中、
日帰り温泉みしゅらんで五つ星がついているのを見て気になっていた高湯温泉「玉子湯」を発見。日帰り入浴は終了していて、後ろ髪を引かれながら山登りを続ける。しかし玉子湯に入れないことを残念に思っていたら、日帰り温泉施設らしきものを発見しそれで我慢することにした。
実は余り期待せずに立ち寄ったのだが、その日帰り温泉は「あったか湯」という高湯温泉旅館共同組合が運営する本格的な温泉で、正直言って今まで多く立ち寄った日帰り温泉の中では最上級、圧倒的に素晴らしいものだった。
どのように素晴らしいかというと、まずお湯が最高。源泉かけ流しで、湯量も豊富。何故玉子湯というのかが合点が行った、綺麗な萌黄色がかった乳白色の湯。露天風呂には檜の樋を使って温度を調整しながらお湯が引かれているのだが、そこには「硫化水素ガスがお湯から出てくるため流出口にはあまり近づかないようにしてください」との注意書きが。泉質はPH2.8という強酸性の硫黄泉。檜の樋の底には薄黄色の硫黄がうっすらと積もっていた。もっとぴりぴりした感触のお湯を想像していたのだが、PHの割には軟らかいお湯で、いつまでも入っていたい気がした。一緒に行った後輩Mも感動していた。先を急いでももうしょうがないのでゆっくり浸かって運転で張ってきた腰をほぐした。
この温泉に入れたのだから天気に恵まれなかったけれども来た甲斐があった、とまで思わせる温泉だった。これで入浴料250円はなんだかこちらが申し訳ないぐらいの感じである。施設も新しく、極めて良いところだった。後から聞いた話では、7人も入れば一杯になってしまう上に地元でもとても人気が高く、ゆっくり入れたわれわれは極めてラッキーだったとのことだった。
満足感に浸り、二人の体から立ち上る湯気で窓を曇らせながら程なく磐梯吾妻スカイラインの入り口高湯料金所に到着。午後5時半。日没はしていないものの、霧で視界は15mもない。この道を通らないと宿に着かないため、1570円を払って料金所を抜けようとしたら、料金所のおじさんに「あんたたちこんな霧の中本当に行くの?1570円も払っても何も見えないよ」と諭された。事情を説明すると、元の道に戻って宿を目指しても余り距離が変わらないと教えられたため、無駄金を遣うことなく仰せの通り来た道を戻ることにした。
結局ホテルに着いたのは6時過ぎだった。1990年に建てられたホテルプルミエール箕輪は、まさにバブルの遺産のような佇まい。トマムや、洞爺湖の某ホテルを思い起こさせるゴージャスさで、調べてみたら案の定ローンスターによって買収されていた。しかしホテルそのものは築14年とは思えないほどメインテナンスが行き届いていた。
夕食はメインダイニングでの洋食を予約していたのだが、チェックインした時に何とドレスコードがあるとの説明を受けた。ジャケットは要らないのだが襟のある服で、ジーンズ不可とのこと。こちらはそんなことはつゆ知らず、思いっきり2アウトの格好である。1アウト目はTシャツ、2アウト目はジーンズ。そんなことだったら予約の時に言うべきであろう。気にならない人は良いかもしれないが、場違いな格好で食事をするのはこちらも気分が良くない。Mはよれよれではあったがポロシャツを着ていたので1アウトで済んでいた。仕方がないので私も奇跡的に持ってきていたポロシャツに着替えた。
どうやら私たちが知らなかっただけなのかもしれないが、メインダイニングでは地元では結構格式高いレストランだったようだ。われわれのように思いっきりカジュアルな格好の人たちもいたが、ちゃんと着飾って食事をしていた人たちもいた。確かに、マルゴーやラトゥールが置いてあるようなレストランだったので、ラフな格好の男二人がテーブルを挟んで向かい合っているのはかなり場違いだったに違いない。食事自体は悪くなかった。またしてもブルゴーニュの白を空ける。
野郎二人でロマンチックな宿に止まっていても何もやることが無いので(あったら結構怖いが)、酔っ払って地下のゲームコーナーでワニワニパニックで裏技を使ってパーフェクトを叩き出し、部屋に戻ってTVの一つも面白くないお笑い芸人のショーに二人して毒づきながら、裏磐梯での夜は更けていった。


朝起きても、ご覧の通り相変わらずの悪天候。仕方が無いのであきらめて磐梯吾妻レークラインを走ることにする。本来であれば観光客が多い道なのだろうが、ほとんど交通量は無い。雰囲気は高原の中の一本道といった感じ。磐梯山の噴火によってできた檜原湖、秋元湖、小野川湖をまとめて望むことが出来るポイントがあり、視界が昨日よりも若干良くなったこと、路面がスリッパリーなことでどちらかというとわれわれの気分も若干観光モードだった。
そのためもあってかわれわれの印象には余り残らないコースだった。
その後西吾妻スカイバレーを抜けて米沢に行くことにした。西吾妻スカイバレーはかなり期待していた。というのも前述したとおり七曲りがあって、ここを駆け抜けてみたい、というのが今回の旅の大きな動機になっていたからだった。しかし標高が上がってゆくにつれ、やはり視界が悪くなってきた。前日のように霧の中を突き進んでいく状態になり、七曲にたどり着いたことすらわからないような状況だった。景色を見るも出来ず、スピードを上げることも出来ないのでフラストレーションがたまった。仕方なく米沢まで走って観光することにした。走っているうちに天気も若干回復。山形県に入る手前で視界も幾分回復してきた。写真をご覧いただくとお分かりになるだろうが、結構な標高である。雲よりもずいぶん高いところにいる。山形県側に突入すると、日本海が光って見えた。福島から山形に向かっていて面白かったのが、山形に入った途端に道が悪くなるのである。舗装の質が、明らかに悪い。ただ舗装した時期が古かったのかもしれないが、ひび割れていたり、路面の質が一様ではなかったりして神経を使う。特に雨の日にポルシェで走るにはかなりの緊張感を強いるものだった。路面の状況に加え、米沢への道はかなりアップダウンが激しくなおかつトゥイスティというチャレンジングなもので、自分の車が四輪駆動であることに感謝する場面が何度かあった。
道の途中に白布温泉というところがあり、前日のあったか湯に味をしめた我々はまた朝の10時になるかならないかという時間にもかかわらず、再び温泉に浸かっていくことにした。白布温泉はこじんまりとした湯の里で、大規模な宿も無く、鄙びた感じが強い。10時からやっているところは「かんぽの宿」しかなく、ほかの宿と比べて近代的過ぎて興ざめだったが背に腹は変えられなかった。
しかし、我々はめったに味わえない体験を味わうことになった。10時という中途半端な時間のため、入浴客はほとんどいなかった。鳥の声しかしない、静かな露天風呂に、一人ぽつねんと浸かっていると、とても幸せな気分だった。そんなゆったりとした気分の中、目を瞑って唸っていると、何か気配がする。目を開けてみると、前方3メートルもないところにある温泉の目隠しの上に大きなオス猿が座ってこっちを見ているのだった。
猿と至近距離で目が合っている状況、それもこっちは裸、というのは当たり前だが経験が無い。野生の猿とは目を合わせてはいけない、とよく言われるが、ガンの飛ばしあいである。それもこちらは超無防備な状態だ。なんせ生まれたままの姿である。まあ33歳にもなるおっさんの裸が「生まれたままの姿」というのは相当厚かましいのは十二分に承知の上だが。無言で睨み合っている時間はとても長く思われたが、恐らく十秒も無かっただろう。猿は突然ふと姿を消した。
今の出来事を、やはりにわかには現実として受け止めにくく、頭の中で反芻していたら、後輩Mが内湯から露天風呂に出てきた。彼に「信じられないかもしれないが」と前置きして何が起こったのか説明したら、最初はやはり半信半疑な顔をしていた。本当だって、とどんな状況だったかを話しているまさにその時、いなくなったはずのサルがなんと二階から雨どいを伝って降りてきた。顔に傷のある、私が先ほど遭遇したまさにそのオス猿だった。さすがに目の前に再び猿が現れると、信じざるを得ない。(サルだけに。)Mも相当びっくりしていた。
なぜ猿が現れたのか考えていたのだが、恐らく猿も露天風呂に人間がいるとは思わなかったのだろう。冷たい雨が降る中、体を温めようと人の気配のしない露天風呂に来てさて入ろうとしてみたら、実は私が一人湯に浸かっていたので、猿も実は焦ったに違いない。
何はともあれいい経験だった。風呂を出て一路米沢を目指した。といっても20分ぐらいで着いてしまったが。かつて訪れたことがあるので土地勘はあった。取り急ぎ上杉神社に参詣して、米沢牛を食べられる店を探すことにした。前回来た時はしゃぶしゃぶを食べたのだが、今回はすき焼きを食べたくなり、持参したラップトップPCで店を検索して、吉亭という店ですき焼きを食すことにした。
登起波という店にもそそられたが、こちらは後輩Mが行ったことがあるというので吉亭にした。吉亭は江戸時代に織物織元だった建物をそのまま活かした、雰囲気のある店だった。上杉神社から至近。裏磐梯に行こう、と思っていたときには全く米沢牛を食べる予定はなかったのだが、一度すき焼きのことを考え始めると二人してどうしても地の卵に霜降り肉を浸して食べることが頭の中から消えなくなった。そもそもあまり福島に縁がないので、裏磐梯から米沢が至近ということすら知らなかったのだ。
我々はすき焼きのコースと牛の刺身を注文。牛の刺身は脂の融点が高いのでトロよりも旨くない、という人もいるが、牛は牛で旨いだろうというのが我々の結論。そしてすき焼き。肉はぱっと見ると一人前が余り多くないように見えるが、実はかなりぶ厚く、食べ応えがある。車で来ているのでがっつり飲めないのがとても残念だった。私は霜降りがきつすぎる牛肉は余り好きではないのだが、ここのお肉はちょうど良い脂の乗り具合で、肉を追加で頼んでしまった。脂がきついとすぐに胸が一杯になってしまうので。
東京で同じクオリティのものを頼むと恐らく一人1万5千円ぐらいは簡単にかかるものが、米沢だと半分強程度ですんだ。すき焼きが食べられるとは期待してなかっただけに、とても幸せな気分だった。
満腹になり、午後2時過ぎになったこともあり、帰路につくことにした。米沢では雨も上がり、西の空が明るくなってきていた。米沢からは、西吾妻スカイバレーに再挑戦し、秋元湖の南岸を通って母成グリーンラインを経由して磐梯熱海ICに抜けることにした。
路面はハーフウエットに変わっていて、視界も晴れて来たのでかなり速いペースで993を駆った。ゆっくり走った往路は余り気にならなかったが、西吾妻スカイバレーはコーナーがタイトな上、勾配がかなりきつい。4駆なので走りやすいが、RRだと後輪のグリップをしっかり意識しないとかなり恐ろしいことになるような気がした。ペースを上げて走る方は、念のためタイヤの溝のチェックをお忘れなきよう。
そして晴れて来たので、念願の七曲りを上から眺めることが出来た。写真で見て凄い、と思っていたが、実際見てみると凄まじい風景である。朝来たときはまったく判らなかった。早朝交通量の少ない時に登りで走ってみたいものだ。下りはコーナーがタイトなので何かあったらエスケープゾーンが少なく、ちょっと勇気がいる。
ご覧の通り、コーナーはやはりブラックマークだらけである。


途中から観光客の車が増えて、つまらなくなってきてしまったので、母成グリーンラインに最後の期待をかけた。そこまでは観光バスの後ろを走らなければならないときもあり、後輩Mは助手席で退屈の余り爆睡していた。
母成グリーンラインは、かなりの高速コースだった。雑誌ではニュルブルクリンクにそっくりだと書いてあったが、行ったことがない私には良くわからなかった。しかし走っているうちに何を意味しているのかはよくわかった。開けた高原の中の一本道で、長い直線の後高速コーナーが連続する。しっかり右足に力を入れれば下手をすると3速レッドゾーンまでスピードが乗るか、と思われるようなスムーズなコースである。気がついたのだが車線の幅がかなり広く、いい感じでセンターラインが剥げているので、自分がサーキットにいったらこんな感じなのだろうな、という感触が味わえるのだ。ここは通行量が少なく、思い切ってコーナーに突っ込んだ後アクセルを開けていくことが出来た。後半はかなりスリリングなコーナーが連続。ここまで横Gが長くかかるコースもそう多くなかろう。いつまでも走っていたいが速く走り抜けたい、という有り勝ちな矛盾を抱えながら、気がつくと磐越自動車道まで着いてしまった。
日曜夕方の東北道は、100km前後で流れているのだが、腹立たしいことに一番右の走行車線を走っている車が少なく、多くが中央車線ないし追い越し車線をだらだらと走っている。何故追い越さないのであれば走行車線を走らないのか、理解に苦しむ。私はどんなに飛ばしているときでも、空いていたら一番右側を走る。オービスに引っかかる可能性も少なくなるし、覆面PCの追尾にも気がつきやすいし、変な車にあおられる危険も少なくなるし、いいこと尽くめだ。ただし、IC入り口やPAなどの合流ではもちろん右に戻るが。車線変更が面倒なのだろうか。前が空いているにもかかわらず後続に道を譲らない車にベンツとセルシオが多いのはどうしてなんだろう。
Next
Back
Index
Home