日々雑感 2006年2月
バブルに関する一考察
スーザン史子さんのHPにGPCの続報が出ていたので眺めていたら、その横にMJブロンディこと清水草一さんのWEB歳時記へのリンクがあり、いろいろ見ていたらとても興味深い記事があった。「フェラーリ イン ザ バブル」という記事である。
そこには、バブル絶頂期に投機の道具となってしまったフェラーリの姿と、それを取り巻く金銭感覚が壊れてしまった人間模様、そしてバブル期の大量輸入とバブルの崩壊が日本でフェラーリの「大衆化」を促したことが書かれている。
バブルの定義は何か。様々な定義が出来ると思うが、私は「価格が上がるとそれに伴って需要が加速度的に増加する、自己実現的な状況(上がるから買う、買うから上がる)が発生し、それに対して人が疑問を抱かなくなった状態」だと思う。たまたま今週の東洋経済にも、「高額消費の爆発 消費バブル再燃か?」という記事が出ていて面白かった。でも現在の状況は局地的なバブルにとどまっていて、それが全体に伝播する状況ではまだないような気がする。
六本木などでは三連休の前など終電がなくなるとタクシーが捕まりにくかったりするものの、朝まで待たされたりすることは当然ないし、中古車の相場を見ていても新車よりもプレミアムがついて並行輸入車が取引される事例もまだ多くない。
 ただし、一部では今までメインストリームでなかったクルマ、例えばマセラティ、ベントレー、アストンマーティンなどが大人気になっていたりしていて、周辺銘柄がにぎわうというバブル期特有の現象が見られる気がする。
ただし、一部では今までメインストリームでなかったクルマ、例えばマセラティ、ベントレー、アストンマーティンなどが大人気になっていたりしていて、周辺銘柄がにぎわうというバブル期特有の現象が見られる気がする。
景気の悪いときには、「ベンツのS320で我慢して、バッヂだけS500に付け替えようかな」と思っていた善良な小市民たるおじ様たちが、ミニバブル到来とともにどんどんリスクをとるようになっていて、ベンツS320→BMW7シリーズ→ジャガーXJ8/Audi A8という順当なエスタブリッシュメントとしての序列(代議士の席次みたいなものですな)を吹っ飛ばして、ベンツS320買う予定だった→いきなりマセラティクワトロポルテをなぜか購入、などという杉村太蔵並みの大番狂わせ、真面目なおじ様が40代にして社会人デビュー、チョイ悪オヤジアクセル全開。的な状況になっているような気がする。
バブル残り香 三兄弟



バブルの時には日産インフィニティQ45や、マツダセンティア(リンク、必見です)、三菱デボネアがチバリーヒルズのように人気大暴騰だった。というか、センティアはバブル終わってから出てきたバブルの残り香のような車だったような気がするが。周辺銘柄が下落するときのスピードはホリエモンの没落より速い。
バブルの頃は日本全体が躁病になった状況だったのだろう。この状況は何だか変だ、と思っていても、変だと言い出せず、これが当たり前だと自分の疑問に対して自分で理論武装してしまい、正道を見誤る。人間には学習効果があるはずなので、過去の異常な状況を見て疑問を抱くことが出来るか、という警鐘の意味もあり、是非上記記事を読んでみることをおすすめする。
この記事へのコメント
箱根で戦う964RSのHP
いつも見ている日之出モータースのHPを拝見していたら、最近出来た神奈川店の店長さんの村上さんが、個人のHPをお持ちだということを発見した。早速見て見たら、これが凄い。ターンパイク、芦ノ湖スカイラインで戦う超武闘派964RSのHPであった。
芦ノ湖スカイラインを心地よく攻めるために、様々なセッティングを試されていて、極右武闘派ポルシェ乗りの方の参考になること間違いなしである。アライメント、サス減衰力、タイヤ空気圧を初めとした様々なセッティング情報が入手できる。ワンオフで製作されたという、高回転域ではフェラーリサウンドもびっくりという等長チタンマフラーがうらやましい。私のような軟弱ポルシェ乗りのHPとは一味も二味も違った切り口。なおかつHPがシンプルかつ機能的で、恐らく村上さんはとても几帳面な方なのではないかと推察される。車の整備の知識があり、整備を行える環境があり、そして運転の腕があるというのがドライバーとしての理想だが、村上さんはその全てをお持ちである。そんな恵まれたポルシェ乗りは世の中広しといえどもそれほどいないのではなかろうか。
この記事へのコメント
最近びっくりしたこと
ワインを飲むことになっているので電車で出社したのだが、大量のサラリーマンの群れがものすごい形相でダッシュする光景に出くわした。朝のラッシュ時の空席取りがあんなに激しいものとは思わなかった。
わたしが使う駅は二線が乗り入れていて、一つが始発駅となっているのだが、反対側の線に電車が到着するや否や、物凄い数の乗客が反対のホームの電車の入り口に向かってダッシュするのだ。サラリーマンのおっちゃんたちが目の色変えて一斉にダッシュする姿なんて、日常そう見られるものではない。競馬のゲートインからのスタートや、スノーボードのダウンヒルクロスのスタートよりも迫力あるぞ。ボーッとドア付近にいた私は突き飛ばされそうになった。また、戦い敗れて席に座れず、それでも席を探してきょろきょろしているサラリーマンを見ると、世の無常を感じる。そんなに頑張らなければならないなら、むしろ20分ぐらいなら坐らない方がましかも。
二つ目。先日会社のトイレで手を洗ったら、ペーパータオルがなくてゴーッと温風の出るドライヤーで手を乾燥させたのだが、急いでいたので何となく生乾きだな、と思ったままエレベーターに乗った。そうしたらニューヨークから来ている社長と、東京の大ボスが乗っているではないか。大ボスから社長(女性なのだが)をエレベーターの中で紹介され、彼女が手を差し伸べてきたので「やばい、手が湿っててどうしよう」と一瞬パニックに。ほんとこういう状況って困りますよね。しかし女性だったので軽く彼女の指先を握ることで何とか急場をしのいだ。心の準備が出来ていなかったのでびっくり+何一つ気の利いたことが言えなかった(女性の手をがっつり握るのは失礼だということを知ったのはわずか数年前のことだったが)。
もう一つ。文芸春秋の最新号を読んでいたら、塩野七生女史が「ハリウッド映画がいかに文化を破壊しているか」について寄稿されていた。タリバンによる仏像破壊と同等のことを西欧文明も行っている、という趣旨だった。その中で、一つの例としてブラピが出演した「トロイ」が如何にギリシャ神話を冒涜するものであるかが述べられていた。具体的には、ブラピ扮するアキレスが、戦いに敗れて死ぬ際、映画のように全身に矢を浴びて死ぬのは間違っている、との指摘だった。すなわち無敵であるアキレスにも唯一弱点があり、そこを矢で射られて倒され死んだことが「アキレス腱」という言葉の由来だったのに、そのような超有名なギリシャ神話すらアメリカ人は知らないのか、それは西欧文明を自己否定するものだという趣旨の記事だった。
しかし、ですよ。壮大な戦いの結果、ブラピ扮する英雄の最後がアキレス腱に矢がぷっすり刺さって敵前で命を落とす、というのはかなり映像的に滑稽ではなかろうか?間寛平の持ちネタで蚊のふりをして「血ぃ吸うたろか」というのがあるが、あれをなぜか思い出してしまった。アキレス腱射られて死ぬ、というのは「豆腐の角に頭ぶつけて死ぬ」ぐらい難しそうだし。そんな結末だったら、観客は2000円も払って映画見ないであろう。塩野女史のご意見は正論であり、ごもっともだが…。結構びっくり。
この記事へのコメント
997Turbo、うーんカッコいい
 ポルシェUSAのHPを眺めていたら、997ターボの特集ページがあって、じっと見入ってしまった。ぜひこちらから、プロモーションビデオを始めとする様々な映像を見ていただきたい。ここでは、917/10がターボエンジンを搭載して1972年にCanAM Championshipを席巻した映像から、930ターボの全力走行など、めったに見られない映像がたくさん見られて興味深かった。また997ターボの新しいフィーチャーについて、かなり細かく文字とFlashで説明されるので、とてもインフォーマティブだ。いつも思うのだが、ポルシェのHPは凄く出来がいい上、映像ライブラリとしての質も高く、感心させられる。実際に購入しようとしている人の背中を押すことが出来るHPのクオリティである。
ポルシェUSAのHPを眺めていたら、997ターボの特集ページがあって、じっと見入ってしまった。ぜひこちらから、プロモーションビデオを始めとする様々な映像を見ていただきたい。ここでは、917/10がターボエンジンを搭載して1972年にCanAM Championshipを席巻した映像から、930ターボの全力走行など、めったに見られない映像がたくさん見られて興味深かった。また997ターボの新しいフィーチャーについて、かなり細かく文字とFlashで説明されるので、とてもインフォーマティブだ。いつも思うのだが、ポルシェのHPは凄く出来がいい上、映像ライブラリとしての質も高く、感心させられる。実際に購入しようとしている人の背中を押すことが出来るHPのクオリティである。
997ターボのエクステリアのハイライトは、19インチのターボ専用にデザインされたホイール(ちょっとAMGのホイールに似ているが)と、フロントディレクションインディケータ(まあ早い話がウインカーですな)がLEDになってフロントエプロンに装着されているところか。カレラ対比アグレッシブ度がかなり増していて、見まがうことは有り得ない迫力である。アグレッシブなデザインとはいえ、CD値は0.31ときわめて低い。
また軽量化も随所で図られていて、ドアやトランクフードはアルミで出来ているらしい。リアサスペンションのダンパーは、スティールではなくアルミのケースになっていて、軽量化とアジリティの向上が図られている。エンジン部品も耐久性と軽量化を両立させる新素材が用いられ、パワーウエイトレシオの向上と、その結果としての高い環境性能を達成している。流石エココンシャスのドイツ人の作る現代の超高性能スポーツカーである。
エンジンは480馬力、最高時速は310km/hだという。2000回転からトルクは60kgを超える上、5500回転まで満遍なくフラットなトルクが湧き上がるということだ。ターボの弱点であった、エンジンの低回転域でのパワー不足は、Variable Turbine Geometryという画期的な技術で解決されている。すなわち、これまでのターボエンジンでは低回転域ではExhaust gas velocityが不足するため過給圧が上がらず、高回転域で過給圧が急に上昇する、いわゆる「どっかんターボ」状態になってしまうが、VTGテクノロジーによってタービンに排気ガスが流入するバルブの形状を電気的に制御し、ざっくり言うと低回転時はバルブの口径を小さくすることで排気ガススピード(Exhaust gas velocityを直訳しているつもり)を上げてブースト圧を高める工夫がなされている。これによって低回転域から高回転域までフラットなトルク特性を可能にしている。詳しくは上述のHPの「Masterwerk」「Act One」「Variable Turbine Geometry」からアニメーションを参照されたい。
また、アフターバーナーのようにスイッチを押すと一時的にブースト圧が上がってサスペンションのセッティングがよりスポーティーになる、昔の野球盤で言えば消える魔球スイッチみたいなものまで用意されているらしく(言っている事があまりに古すぎて意味判らない、という方はリンクをクリック)、ライバルを戦意喪失させるアイテムには事欠かない。
最新のポルシェは、最上のポルシェ、というのは、マーケティング上の殺し文句だけではやはりないようだ。愛車がどんどんクラシックカー化していく気がしてきてちょっとさびしい。
この記事へのコメント
ジャガー納車から1ヶ月
ジャガーが我が家に来てからおよそ1カ月。一昨日葉書が来て、アルファ号の名義変更が終わったとのことだった。今でもアトランタブルーのZ3が走っているのを見ると、昔の愛車かどうかディテールを確かめてしまうのだが、同じように真っ赤なアルファ147を見るとつい(元)愛車の面影を探してしまう。元カノを忘れられない女々しい男のようだが。いい人(男?)に貰われて行ったのなら良いのだが。エンジン、思いっきり回しておきましたから超スムーズに回るはずですよ、新オーナーさん!
1カ月経ってジャガーに対する印象は何も変わらない。ずっと乗っていたくなるのだ。昔は会社にアルファで行きたいと積極的には思わなかったが、今は深夜でもタクシーに乗るより自分の車で帰りたいと思う。特に何かがず抜けていい訳ではないのだが、何だか落ち着くし、もっとハンドルを握っていたいと思わせる何かがある、不思議な車だ。これが高級、ということだろうか。でもこの感情を説明しろ、といわれてもなかなか言葉にできないのだ、これが。
唯一気になるのが、ゴルフバッグを積むと乗り心地が悪くなった気がすること。荷重が掛からない方がしなやかな味付けのエアサスペンションなのかも知れない。それ以外はあまり不満がない。アルミボディは明らかに加速の良さに貢献している。しかしアルミボディであることを実感するのは、発進加速の良さというよりは、ボンネットを閉めるときの何とも言えないアルミ独特のふにゃっとした感触。また、フロントフードが軽いため、強い向かい風の吹いたアクアラインをすっ飛ばして走った際、運転席側のフードの端が空気抵抗で大きく震えていたのにはびっくりした。料金所横で車を停めて、しっかりフードのラッチが止まっていることを確認してしまったほどだ。
2年弱で1800kmしか走っていなかったのに、すでに我が家に来て1カ月で走行距離が1200km延びて3000kmにもなろうとしている。こんな人遣いの荒い家に貰われてくることは想定外だっただろう。でも、本当にもっと乗っていたいと思わせる車だ。会社に着いても、そのままどこかに行きたくなる。ただ単に出社拒否したいだけだったりして。
この記事へのコメント
車の電子制御化の功罪
 少し前の話になるが、年末年始はサンフランシスコに旅行に出掛けた。現地はあいにくの雨、というよりむしろ嵐といった方がいいような天候だった。酷い雨と風は数日続き、ゴルフもできず、退屈してナパかソノマのワイナリーでも行こうかと思ってテレビのローカルニュースを見ると、ナパでは川が氾濫して洪水になっているという。あっという間に街の至る所が浸水したらしい。
少し前の話になるが、年末年始はサンフランシスコに旅行に出掛けた。現地はあいにくの雨、というよりむしろ嵐といった方がいいような天候だった。酷い雨と風は数日続き、ゴルフもできず、退屈してナパかソノマのワイナリーでも行こうかと思ってテレビのローカルニュースを見ると、ナパでは川が氾濫して洪水になっているという。あっという間に街の至る所が浸水したらしい。
ニュース番組で実際にその現場に居合わせたキャスターが、自分の体験を語っていたのだが、その内容はクルマの安全性の根本にかかわる問題だった。
彼は街を日本車「O(国内名F)」というSUVで走っていて、浅い水溜りは普通に踏破できたのだが、そのうち水溜りが濁流に変わってしまったそうだ。そして気が付くと車ごと流され始め、脱出を試みようとした。ところが、車内に水がどんどんと入ってきて溺死の危険が現実のものとなる中、オートロックのドアが開かず、オートウインドウも開かず、パニックになり、あわや車とともに水没するところだった、と述べていた。
SUVは水深のある川の中に突入していくことを想定して設計されているわけではないだろうから、今回起こったことは想定外の不幸な出来事であると片付けてしまうのは簡単である。設計で前提にしている条件から著しく離れた現象が発生したため、想定外の事態が起こりました、と言い訳することは出来るかもしれない。しかし、発生確率が極めて低くても、発生した場合には致死率が極めて高いような状況を、メーカーとして許していいのだろうか。ここではフェイルセーフは用意されていなかったようだ。(本当かどうか知らないが、タイの大蔵大臣の乗ったBMW7シリーズのオートロック、オートウインドウとも故障して、大臣が閉じ込められ、通行人がハンマーでガラスを割って救出したというAP電もあったらしい)
車はどんどん電子制御化されていく。メルセデスのセンソトロニック・ブレーキ・コントロールがそのいい一例である。もはやペダルの踏力が油圧でブレーキディスクに反映されるわけではなく、踏力を電気信号にして伝達し、制御用コンピュータが油圧でブレーキをかけるようになっている。コンピュータの制御に問題があったり、電源が止まってしまった場合は、フェイルセーフとして従前どおりペダルから油圧で機械的にブレーキを掛けることができるようになっている。ご承知の通りセンソトロニックは初期にトラブル続出で、メルセデス史上最大のリコールを引き起こすこととなった。こんな例もHP上で報告されていた。機械式ブレーキも効きが甘く、フェイルセーフ性が著しく低かったということである。
最近私が購入したジャガーも、あるHPを見ていたら、トランクのオートクローザーが故障して、旅行先でトランクに入れた着替えとゴルフ道具が取り出せなかった、というトラブルがあったとのこと。これは先ほどのブレーキトラブルと比べればまだかわいい方だが、機械的にトランクを開けられる機構があればこんなことは起こらなかっただろう。
電子制御自体に反対する積もりは毛頭ない。お風呂が自動給湯じゃなければめんどくさいのと同様に。ただし、自動給湯システムが壊れたら即マンションの下の階に水漏れ、では困ってしまう。
走る、曲がる、止まるという車の基本に関しては一系統が故障したとしても、バックアップシステムが当然あって然るべきだし、緊急時に生命に関わるような機構(ドア、ウインドウ)などもフェイルセーフ完備であることが当然望ましい。
当然二系統用意すると、車の重量増、居住性の悪化などの悪影響が出ることは承知の上だが、その悪影響を考えてもなお、電子制御にすべきかどうか、そのメリットがあるのかを考えながら電子制御化してもらいたいと思う。部品メーカーや、エンジニアのマスターベーション的電子制御化(とその弊害)は真っ平である。
この記事へのコメント
第1回自動車雑誌編集部員&自動車メーカー関係者ポルシェ愛好家ミーティングへの参加
今度の日曜日は、東京近郊某所でポルシェ乗りの方が集まるミーティングに出掛けることになっている。それもただのミーティングではなく、自動車評論家や自動車雑誌の編集者の方々、ポルシェジャパンの広報部長の方など来られる中、素人は私一人という状況になる予定。面子が何と言っても凄過ぎる。あの清水和夫さん、吉田匠さんや中谷明彦さんなどそうそうたる面々が、仕事でもないのにただのポルシェ好きの集いに顔を出されるのだから凄いことだ。私だけ肩書きが「紺ガエル日記HP主宰」ですって。全然肩書きになっていないかも。
私は清水和夫さんの理知的なのにアウトロー臭が漂うところがとても好きで(つまりインテリヤクザっぽいということだが)、彼にお目に掛かれるなんて嬉しくて仕方がない。この集いは、某自動車雑誌編集者のOさんがこのHPのメールアドレスにメールを送ってくださって、年賀のご挨拶を差し上げたら何故だかトントン拍子に話が進んだのである。ありがとうございます。
しかし、愛車はフロントサスのへたりが気になってきつつあるので、そんなハレの場に連れ出すのがちょっと気恥ずかしい気がしているのも事実。PC目黒の小塚さんに足回りのリフレッシュの費用はどれぐらいになるか教えていただいたら、やはり予想通り50万円コースだそうだ。
先日ダイムラークライスラーの広報の方とお話させていただいたら、「メーカーがニュルを含めて何十万kmも走りこんでセッティングしたサスペンションよりも街中のショップのサスペンションの設定の方がいいことは有り得ない」と断言されていた。つまりディーラーでの純正部品への交換がベストだということである。極めて説得力あるご意見である。サーキット走行をするならともかく、私のような軟弱ストリートファイター(嘘)にはやはり純正のサスペンションがいいのかな、とも思うし、ディーラー以外に持っていくと恐らく半額程度でリフレッシュしてもらえるはずなのでタイヤ1セットを新調してもおつりが来ることを考えると悩ましい。
皆さんのハイレベルな会話に付いて行かれなかったらどうしよう、とチキンになっている今日この頃である。ミーティングのあとは食事会もあるらしいので。基本的にはOさん以外どなたも存じ上げない。しかしもしかしたらついに念願の(?)自動車ライターへの道が開けるかも…なんて調子のいいことを考えているのだ、実は(笑)。
なーんてことを書いていたら、幹事的存在であるOさんが締め切り直前で仕事が山積していて、もしかしたら来られない可能性があるというメールが飛び込んできた。そうなると私と河口学氏が今回のミーティングを仕切らなければならないらしい。そうそうたる面々をわたくしごとき青二才が仕切れるのだろうか…。まあ日々の仕事に比べればまだ楽かも、と思うことにしよう。
GPC(ギョーカイポルシェクラブ)参加記はこちら
この記事へのコメント
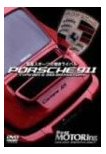
国産スポーツの憎きライバル PORSCHE911 TYPE964&993 BM HISTORY
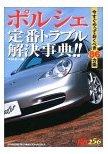
ポルシェ定番トラブル解決事典!!―今すぐやっておくべき86カ条
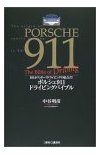
ポルシェ911ドライビングバイブル―RRがスポーツドライビングの原点だ!
