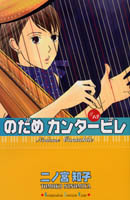
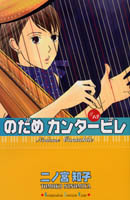
10年以上マンガ全巻を読破する、ということをしなかった私が、なんと、少女マンガを13巻まとめ買いして一日で読破してしまった。4巻読破して、続きがあることを知っていそいそと本屋に行き、家に帰るのももどかしく、カフェに残り9巻を積み上げて人目を気にせず表紙にカバーも掛けずに完読。そのマンガとは、のだめカンタービレ
。マジはまりである。
このマンガが連載されている雑誌は、講談社のKissという雑誌らしいのだが、ご丁寧に雑誌のロゴの上に小さく"Love Story Comic For Young"と書いてある。そもそも私のようなおっさんは読者として想定していない世界のマンガ雑誌らしい。
昨日渋谷のHMVのクラシックコーナーに立ち寄ったら、このマンガが全面的にプッシュされていた上、この本にフィーチャーされていたブラームスの交響曲第一番がこのマンガの主人公である指揮者の意図の通りにオーケストラ演奏されているCDというのも売られていたりして、かなりびっくりした。500万部も売れているらしいので、何をいまさら、このジジイ、と思われた方も多くいらっしゃるかもしれない。
それはともかく、このマンガには「音楽を譜面どおりに弾くこととはどういうことか」、すなわち「各人がそれぞれ好きにある曲を解釈することと、譜面どおりに弾くことは両立するのか」、「本当に音楽が好きな人が、ある決まりに従って型にはめられて演奏することで、音楽を嫌いになってしまうということはおかしいことではないのか」という主題を何度もなぞりながらエピソードが展開される。私のような凡人は、譜面通りに楽器を弾くことで四苦八苦しているが、それを超えた境地にいる人の悩みもつづられていて、それが一般的な読者が上手く共感できるような表現方法で描かれている。また、筆者は意図的に前面に押し出すことを避けているのだろうが、クラシック音楽の素晴らしい世界をより多くの人たちに理解してほしい、という想いが見え隠れする。私は子供の頃から親が家でクラシックを聴き倒していたので、決してクラシック音楽は私にとって縁遠い世界ではないのだが、また好きなCDを聞き返したくなった。うちの親にも読ませてみようかな。秋の夜長にお勧めである。といってもあっという間に読破してしまったのだが。
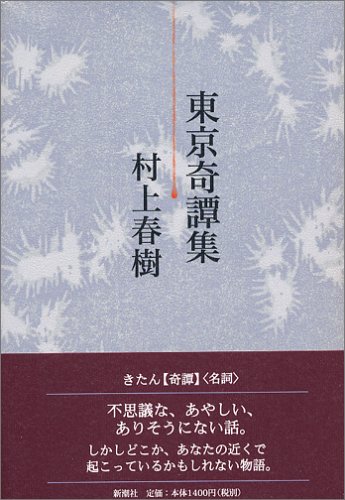
今、実は村上春樹全作品集1979-1989を読破しようとしている。ある作家の全集を読むのは初めてのことだ。昔から村上春樹は読んだことがあったのだが、昨年アフターダークを読んで不思議な読後感に取り付かれ、少年カフカで完全にノックアウトされ、その後ねじまき鳥クロニクルなど過去の作品にさかのぼり、ついにデビュー作から時系列的に読もうと決心することとなった。
そして世界と終わりとハードボイルド・ワンダーランドまで辿り着いたのだが、難解なこの作品に若干疲れてきたとき、彼の新作、東京奇譚集が発売されたのでこちらを手に取ることにした。
これまで彼の時に難解な長編小説を、何度もページを繰りなおしてその複雑に織り成されたコンテクストを理解しながら読んできた身からすると、今回は短編集で極めてすんなりと頭に入ってくる。特に、五つの短編の中の冒頭の「偶然の旅人」という作品は、極めてよく出来ていて、外出中に読んだにもかかわらず涙がこぼれそうになった。村上春樹の作家としての苦悩が、小説家の主人公の言動から垣間見れるところもあったりして、ディープな村上春樹ファンも楽しめるし、入門として読むにも極めて読みやすい。
最近は家も手狭なので、近い将来読み返したくならないと思われる本は読了後即座に古本屋に売ることにしているのだが、当然に手元においておくことにした。村上春樹の本は売ったことはないのだが。
Lexusが逆上陸、8月末から営業を開始した。実はうちから車で5分ほど行ったところ、渋谷は神泉の交差点の角にLexus渋谷がある。
まだ一度も入ってみたことはないが、自意識過剰かもしれないがポルシェで乗り付けると大層もてなして貰えそうな気がする。欧州プレミアムブランドに乗る30代前半の兄ちゃんが、Lexusへの乗換えを検討、などというとまんまとトヨタの作戦に引っかかった消費者の一人になってしまいそうである。
レクサスブランドで欧州のプレミアムブランドに愛知の会社が挑戦する。仮想敵はメルセデス・ベンツであり、BMWであり、またジャガーなのであろう。アメリカにはプレミアムブランドというものは存在しているのだろうか?アメリカ人の間ではそれがキャデラックあるいはリンカーンなのかもしれないが、グローバルには全く通用しない。では、いったい欧州のプレミアムブランドとはなんなのか。
私はアメリカの会社で自分のキャリアを始め、欧州の会社に移籍し、そして今またアメリカの会社で働いている。彼我の文化の違いというのはそれなりに意識しているし、日常的に仕事でロンドンの人間と話し、ニューヨークの人間とも話し、欧州とアメリカの違いについて肌で感じる立場にいる。
では実際に何が違うのか。一ついい例がある。
私の働く業界で、最も米国系と欧州系の違いが端的に現れるのが、会社の受付のインテリアである。一流の米国系の会社の受付は、壁には豪華な木目をふんだんに見せ付け、応接のソファもクラシックなデザインで例えば豪奢な刺繍がなされたシルクが張られたものだったりする。照明は様々なケースがあるが、若干薄暗くしてなにやら秘密めいた雰囲気を演出しているケースもある。床も本物の木をぴかぴかに磨き上げている場合もあれば、その場で足を前後させると靴が磨き上げられてしまうのではないか、と思しきほどの毛足の長いカーペットが敷き詰められていたりする。濃茶色の木の壁に、濃紺のカーペットが敷き詰められ、薄暗い照明で来客に感銘を受けることを強制する。すなわち、米系の会社では、ひたすら重厚感を演出しようとする傾向が見受けられる。 これに対し、欧州(大陸)の会社の受付は、限りなくモダンである場合が多い。照明も明るいし、重厚感というよりもモダンなインテリアで、きわめてコンテンポラリーである。余談になるが、ドイツ系の会社は第三帝国時代にユダヤ人から収奪した可能性がある絵画などを所有・展示できないがために、戦前の絵画などをインテリアに用いることはできず、したがって必然的にモダンにならざるを得ないという後ろ暗い歴史上の事情がある。
では、米国系と欧州系のこのアプローチの違いは何であろうか。私には、歴史に対するコンプレックスに思われる。欧州は、いうまでもなく複雑に彩られた長い歴史を持っており、ことさらに格の高さを声高に主張することなく、過去の経緯が自らのプレステージを証明してくれる。たとえば、金融機関であればイギリスの戦費の調達を助けてその見返りに創業者とその一族が爵位を受領した、など。当然にしてその事実は誰もが知っていて、その会社の顧客は選良である。したがって、外見を重厚に演出することによって自らが「ブランド」であることを示す必然性がない訳である。
これに対して米国は、たかだか200年ちょっとの歴史しか持たず、自らの格の高さを主張(+演出)する必然が存在する。確かに第一次世界大戦のフランスの戦費調達を助けたことでパリのVandome広場に土地を持つことを許された会社などが存在するが、所詮は20世紀に入ってパクスアメリカーナが始まってからの出来事である。したがって、仮に「ブランド」というものが存在していたとしても、それに対して裏書がなされていない。確固とした哲学があったとしても、それは綿々とした時間の経過で試されない限り、哲学として認められない。つまり、自分で演出しない限りは人がそれを「ブランド」であると認知しないのだ。階級社会からドロップアウトした人々が建国した国に、プレステージを誇示するための手段である「ブランド」というものはそもそもなじみようがない。
考えても見るがいい。自分の持っているいわゆる「ブランド物」の中で、アメリカ製のものがどれだけあるだろうか。Louis Vuitton?Gucci?PRADA?Vacheron?大体がフランス・イタリアを中心とした欧州のものである。米国の一流のブランドで思いつくのはごく限られ、例えばHarry WinstonやRalph Lauren程度である。
ではクルマの世界で「ブランド」として認知される必要条件は何であろうか。あるいは、例えばブランド間でのプレステージの差が明確に存在する欧州車の世界では、何がその差を形成しているのだろうか。果たしてそのような閉鎖的社会の中で、たかだかデビューして十数年の歴史しか持たないLexusが、欧州の一流のプレミアムブランドと対峙していけるのだろうか。
ブランドがプレミアムブランドだと認知される条件の一つは、間違いなくレース活動とその実績だろう。フェラーリ、ポルシェ、ジャガー、メルセデス、どれをとってもレースフィールドにおける長い歴史があり、そこではブランド間の面子を賭けた争いが存在し、勝つことによってのみ既存の階級社会の中での確立された順位付けをひっくり返すことができるという暗黙の了解があった。
もう一つは、いわゆる「伝説」の存在である。エンツォ・フェラーリ。フェルディナント・ポルシェ博士。512BB。Dino。アイコンとなっている存在が、そのブランドにあるのかないのか。車の出来ももちろん重要だが、その車とともに語れるだけのエピソードがなければ、その車をブランドと呼ぶことは出来ないだろう。正直言って、車をただの移動の手段としてだけで捉えるのであれば、VitzやIstで十二分であろう。でも、人はそれ以上のものを車に求めている。例えば時間が知りたいだけならば、台湾製の380円のデジタル時計で十分ことは足りる。しかし世の中には、トゥールビヨンだの、ミニッツリピーターだの、永久カレンダーだのがついている時計に、1000万円を超える金を払う人間がいる。それと同様に、車には移動手段という機能以上のものを人は求めている。
翻って、ここでLexusは何を持っているというのだろう。歴史は、明らかに、ない。レース活動の実績?ToyotaブランドでF1を戦っているが、あくまでもToyotaブランドであり、LexusはToyotaから一線を画すブランド戦略である。ToyotaのF1活動は、この意味で極めて矛盾感が強いものとなっているように思われる。F1を見ている観客層は、欧州とアジアであって、米国ではない。ToyotaのイギリスでのHPを見てみると、最もスポーティなモデルでMR-S。最も高価な車でランドクルーザー。F1活動はトヨタの全体的なイメージアップにはなるかもしれないが、プレミアムスポーツカーの販促には全くなりえない。次にトヨタがプレミアムスポーツカーを出してくるということになると、それは間違いなくLexusブランドの下になるはずであり、海外での「トヨタ=高品質・低燃費だが安い車」というイメージからの脱皮を図りたいがためにLexusブランドを作ったのに、F1での活動によって「トヨタ≒Lexus ∴Lexusは高品質・低燃費だが安い車」という近似式が成り立ってしまい、Lexusブランドを育成するためにとんでもない金をかけていること自体が極めて矛盾的行為となってしまう。
またLexusには伝説といえるものは何もない。海外の著名な自動車会社のHPと、日本の自動車会社のHPの最大の違いの一つは、「History」という項目である。トヨタのHPでは「沿革」となっていて、あたかも歴史の教科書の年号表のように淡々と事実関係が述べられている。それに比べ、例えばポルシェのHPではかつてのレースの歴史、歴代のモデルについての詳細な説明を見ることが出来る。すなわち、ポルシェの車を買おうという消費者は、今そこにある2005年製の997を買うだけではなく、これまでのポルシェの歴史と伝説を買うということになる。日本車の中でも、この歴史と伝説を買うことが出来るのはHondaの車を買う消費者だけではなかろうか。本田宗一郎という伝説。F1での歴史。そういったものがLexusには何もない。
Lexusが逆上陸してくるのは、欧州ではなく、米国からである。先に述べたように米国でグローバルに通用するプレミアムブランドというのはほぼ存在していない。日本も、米国も、(旧来の意味での)階級社会ではない。米国から日本に逆上陸し、欧州のプレミアムブランドと正面から戦おうというのは、長靴履いて100m徒競走に一番になるほど難しいように思われる。2004年のLexus車の販売台数は、米国で29万7000台、欧州で2万5000台というこの数字が、何よりも雄弁に物語っているように思われる。
奇しくもLexusのブランド企画室長が、ENGINEの記事で以下のように語っている。「結局、スイスの時計メーカーは高級なモノを作り、”文化”とともに販売し、成功しています。消費者は時計という機械や機能にだけお金を払っているんじゃない。」さらに彼はこう続ける。「レストランでもそうですが、ご飯、料理だけにお金を支払うわけじゃない。器だったり、お店の雰囲気だったり、給仕のサービスだったり、トータルの面にフィーを払っているんです」
この人は大きな勘違いをしている。Lexusの車を買ったらついてくる「文化」というのはいったい何なのか?彼がここで述べている、「レストランの雰囲気」や「サービス」と同等なものは、Lexusでいうと何なのか?
前述したように、Lexusには何のAttachmentもない。多少はあるかもしれないが、欧州のプレミアムブランドと比較して見れば、何もないのと同様であろう。したがって、現在進行形のものに頼らざるを得ず、したがってLexusのオーナーであることに誇りを持てるように、販売店やアフターサービスの現場で受ける接客を磨き上げようとしているのだろう。
それはそれで論理的な展開ではあるように思われるが、大きな見過ごしがあるように思われてならない。それは、レストランでは料理が美味しいことは当たり前で、その上でサービスが行き届いているととても満足できるが、それらは極めて内面的なことだ、ということだ。美味であるとか、快いサービスからの満足感などは、自分がどう感じるかで決まってくるものであり、他人の介在する余地はない。これに対し、車を買うということには、レストランでの食事とは全く違うファクターが存在する。車を買うということは、自分の満足を買うということだけではなく、その車を選んだあなたに対する他人の評価を受けて立つ、ということでもある。ファッションが好きな人が、家の鏡の前で自分の好きな服を来て自分にうっとりするだけで満足するだろうか。街に出て、人に見られることで、より充足感を得られるのではなかろうか。車も同様だ、ということを彼は気がつかないのだろうか。如何にLexusの店に行って重厚な接客を受けたとしても、それはオーナーの内面にとどまるものであり、その満足感はLexusの販売店に足を運んだことのない他人からは全く気づかれない類のものである。自分の好きなクルマに乗っていることを人に見られ、他人からの無遠慮な視線をも快感に変えることこそが、プレミアムブランドを所有することの宿命あるいは使命ではなかろうか。内面だけにこだわる、というのはプレミアムブランドであることを否定するような行為に思われてならない。
では、Lexusはどこへ向かえばいいのだろうか。私が先ほどあげた、プレミアムブランドを構成するための必要条件を考えて見ると、「レース活動の実績」と「伝説の存在」の両者とも、「過去」の話である。VWがBentleyを買収する。FordがJaguarを買収し、Aston Martinを買収する。これは金で歴史を買っている。だが新たなブランドを立ち上げるにあたっては、歴史は金で買えない。Lexusという新しいブランドを立ち上げるのであれば、「未来」をそのブランドの味方につけなければ話にならないだろう。Lexusよ、くだらない接客技術を磨いている暇があったら、その車に「未来」を武装しろ。Toyotaの誇るハイブリッドテクノロジーを、一刻も早く搭載しろ。ハイブリッドの重厚なトルク感を、燃費のためだけでなく高級感の演出に使え。エコロジーコンシャスであることが今の若い知的エスタブリッシュメントにはプレステージャスなことであることに早く気がつけ。低燃費で高性能であることで、これまでのメルセデスを筆頭とした巨艦主義の車を好む層はAncient Regimeにしがみつく層だというレッテルを貼ってしまえ。自らの比較優位を考えてもみろ。どう考えてもテクノロジーであろう。前車をソナーで追尾し、ガードレールと車線を自動で認識し、カーナビと完全連動する変速システムを装備し、縦列駐車は自動でこなせるだけのテクノロジーは既にあるはずだ。「未来の車」をわれわれの前に提示することによって、欧州のプレミアムブランドを「過去の栄光にしがみつく人たちが乗る車」に貶めよ。テクノロジーの力を持って、これまで実現したことのない別世界の安寧な移動空間をわれわれの前に見せ付けろ。そして、欧州のプレミアムブランドが太刀打ちできない価格で、「未来の車」を現実のものにしてしまえ。そうすれば、そこに新しい伝説と歴史が生まれるであろう。
最近おかげさまで順調にアクセス数を伸ばしているとともに、Googleでも結構いいところでHitするようになってきた。
例えば
カレラ4Sで検索をかけてみると、約15,800件中3位(以下、全て9月11日現在)にランクされる。何と恐れ多いことか。
嬉しがって色々やって見ると、
993カレラ4Sだと見事に1位ゲット。ただし約412件中だが。でも素直に嬉しいぞ。
ポルシェ
993だと第8位。約30,000件中からで、なおかつ空冷大魔界さんのすぐ下。名誉なことである。
面白いので、何か他にググって1位になれるものがないかと探していたら、
プレミアム きのこの里で堂々の第1位(日々雑感8月参照)。でも余り嬉しくない+本HPの趣旨に全くそぐわない。ちなみにプレミアム たけのこの里でも第1位で、堂々のダブル受賞(?)。
本HPの趣旨に則っていくと、
Aston Martin Vantage 993で検索かけると1位というのは微妙に嬉しい。
しかし、流血 脳天 血まみれというキーワードでググって見ると、スポニチアネックスの「テリー(右)を血まみれにするブッチャー(中)を後ろから殴る大仁田」という記事を押しのけて何と堂々の1位獲得。喜んで良いのか悲しんで良いのかよく分からない結果となった(泣)。
2005年8月の日々雑感へ
2005年10月の日々雑感へ
Home